- ステーブルコインって何?
- ステーブルコインと他の暗号資産の違いを知りたい
- ステーブルコインの買い方を教えてほしい
ステーブルコインは法定通貨や金などに価値を連動させ、価格の安定を目指す暗号資産の一種です。値動きの大きいビットコイン等とは役割が異なり、送金や決済、DeFiでの担保など実用的な用途で存在感を増しています。
本記事では、ステーブルコインの仕組みや種類、暗号資産との違いをわかりやすく整理し、実際の買い方や選び方、注意すべきリスクまで丁寧に解説します。まずは基礎から順を追って見ていきましょう。
安心して使える国内取引所で暗号資産を始めたい方は、下のボタンからbitFlyer(ビットフライヤー)公式サイトへアクセスして、無料口座開設をしてみましょう!
ステーブルコインとは?初心者向けにわかりやすく解説

暗号資産の価格は日々大きく変動しますが、ステーブルコインは価格が安定しているのが特徴です。ここではその理由や代表的な種類を紹介します。
ステーブルコインの定義
 tk
tkステーブルコイン(Stablecoin)とは、「安定した価値を持つ暗号資産」のことです。ドルや円などの法定通貨や金などの資産に価値が裏付けられているため、他の暗号資産に比べて価格の変動が小さいのが特徴です。
具体的には、「1ステーブルコイン=1米ドル」に価値を固定する仕組みを採用しているものが多く、決済や送金、資産保全の手段として広く使われています。
なぜ「価格が安定」しているのか
ステーブルコインの価格が安定している理由は、主に以下の3つの仕組みに分類されます:
1. 法定通貨担保型
米ドルやユーロなど、実際の法定通貨を担保として保有し、同じ価値で発行されるタイプです。
例:USDT(テザー)、USDC(USDコイン)
2. 暗号資産担保型
ビットコインやイーサリアムなど、他の暗号資産を担保にして発行されるステーブルコインです。
例:DAI(ダイ)
価格安定のために**過剰な担保(オーバーコラテラライズ)**を設定することが多いです。
3. アルゴリズム型(非担保型)
担保資産を持たずに、プログラムによって供給量を調整することで価格を安定させる仕組みです。
このタイプは不安定になりやすい傾向があり、過去に崩壊した例もあるため注意が必要です。
ステーブルコインは暗号資産初心者にも安心な選択肢
ステーブルコインは、価格が安定しているため、「暗号資産のボラティリティが怖い」という初心者にも使いやすい資産です。送金・決済・保管・DeFiなど、活用シーンも多く、今後さらに重要性が増すと予想されます。
ステーブルコインとビットコインの違いとは?暗号資産との比較


「ビットコインとステーブルコインって、どっちも暗号資産なんでしょ?」と思う方も多いかもしれません。たしかに両者はブロックチェーン上で取引されるデジタル資産という点では共通していますが、目的や機能はまったく異なります。
ここでは、代表的な暗号資産であるビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)と、ステーブルコインの違いを詳しく比較していきます。
ビットコインやイーサリアムとの違い
主な違いの比較表
| 項目 | ステーブルコイン | ビットコイン / イーサリアム |
|---|---|---|
| 価格安定性 | 安定(1ドルなどに固定) | 変動が大きい(ボラティリティ高) |
| 目的 | 決済・送金・保全 | 投資・投機・価値の保存 |
| 発行主体 | 民間企業 or 分散型プロトコル | 分散型ネットワーク |
| 担保 | 米ドルや暗号資産など | 基本的になし(価値は市場次第) |
| 規制 | より規制に準拠しやすい | 一部国では規制強化の動きも |
ステーブルコインは価格が安定しているため、日常的な支払い・送金・取引の中継通貨として使用されることが多いです。
一方で、ビットコインやイーサリアムは「価格が上がることを期待して保有する」目的が強く、投資対象として人気があります。
投資目的 vs 価値保存/決済手段


ビットコインは、「デジタルゴールド」とも呼ばれ、将来的な価格上昇を狙う長期投資の対象として広く認識されています。同様に、イーサリアムもスマートコントラクトの基盤として成長しており、投資商品としての側面が強いです。
それに対して、ステーブルコインは価格変動がほぼないため、
- 日常的な決済・送金の手段
- 資産の一時保管場所(特に市場の暴落時)
- DeFiでの取引や貸出に使う担保資産
として活用されます。
つまり、「価格上昇を狙う投資」ではなく、「安定した価値を持つ通貨」としての使い道が中心なのです。
価格変動リスクの比較
ボラティリティ(価格変動)の違い
- ビットコイン:1日で数%〜10%以上の値動きも珍しくない
- ステーブルコイン:1ドル付近で安定、変動はほぼゼロ(ただし例外あり)
価格変動が激しいビットコインは、高リスク・高リターンの資産です。投資には大きな利益が見込める一方、急落による損失のリスクもあります。
一方、ステーブルコインは価格が安定しているため、リスクを抑えた資産運用や資金管理が可能です。特に、仮想通貨市場の下落時に「避難先」として利用されることが多く、投資家にとっても重要な存在となっています。
違いを理解して正しく使い分けよう
| ステーブルコイン | 安定した価値。決済・送金・保全に強い |
|---|---|
| ビットコイン・イーサリアム | 値上がり益を狙う投資対象として有望 |
ステーブルコインとビットコインは、どちらも暗号資産ですが、目的や使い方が大きく異なります。投資・決済・資産保全など、自分の目的に応じて正しく使い分けることが、賢い資産運用の第一歩です。
ステーブルコインの種類と仕組み|USDT・USDC・DAIの特徴を紹介


ステーブルコインとひとことで言っても、実はいくつかの種類や発行の仕組みが存在します。それぞれのステーブルコインは、**どんな資産を裏付けにしているのか(担保)**によって分類されます。
ここでは、代表的なステーブルコインとその種類、仕組みの違いをわかりやすく解説します。
法定通貨担保型(例:USDT, USDC)
● 概要
実際の法定通貨(主に米ドル)を担保として保有し、その価値を1:1で裏付けるタイプのステーブルコインです。
このタイプは現在、最も流通量が多く、取引所でも一般的に使われています。
● USDT(Tether)
- 最も取引量の多いステーブルコイン
- 米ドルと1:1で価値が連動
- 発行元:Tether社
- 世界中の仮想通貨取引所で広く利用可
● USDC(USD Coin)
- Circle社とCoinbaseが共同で開発
- 米国の規制を意識した透明性重視の設計
- 月次監査レポートの公開など信頼性を高める取り組みを実施
● 特徴
- 法定通貨による安定性
- 発行主体の信頼性が重要
- 中央集権的(管理者が存在)
暗号資産担保型(例:DAI)
● 概要
こちらは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を担保として発行されるステーブルコインです。
市場価格が変動する資産を担保とするため、**過剰担保(オーバーコラテラライズ)**が基本です。
● DAI(ダイ)
- MakerDAOという分散型プロジェクトが発行
- 主にイーサリアムやその他トークンを担保にする
- 完全に分散型のステーブルコイン
- 中央の管理者が存在せず、スマートコントラクトで運営
● 特徴
- 非中央集権的(DeFi向け)
- 担保資産の価格変動リスクがある
- 複雑な仕組みを理解する必要あり
アルゴリズム型(例:USTなど)
● 概要
価格を安定させるための担保資産を持たず、アルゴリズムによって供給量を調整するタイプのステーブルコインです。
プログラムで自動的に需給バランスを調整し、価格を1ドルに近づける仕組みです。
● UST(TerraUSD)
- かつて人気のあったアルゴリズム型ステーブルコイン
- しかし、2022年に崩壊(デペグ)し、大規模な市場混乱を引き起こした
- ステーブルコインのリスクとして現在も語られる代表例
● 特徴
- 担保を必要としないため資本効率が高い
- ただし、価格維持に失敗すると暴落のリスクが非常に高い
- 一部のプロジェクトでは依然として実験的に使用されている
各タイプのメリット・デメリット
| タイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 法定通貨担保型 (USDT, USDC) | ・価格が非常に安定 ・初心者にも使いやすい ・取引所対応が豊富 | ・中央集権的 ・発行元の信用リスク |
| 暗号資産担保型 (DAI) | ・分散型で検閲耐性が高い ・DeFiに最適 | ・仕組みが複雑 ・担保資産の価格下落リスク |
| アルゴリズム型 (USTなど) | ・資本効率が高い ・革新的な仕組み | ・価格安定に失敗するリスク ・実績が不十分で信頼性が低い |
目的に応じてステーブルコインの種類を使い分けよう
ステーブルコインには複数のタイプが存在し、それぞれ特徴やリスクが異なります。日常の取引や送金にはUSDC、DeFiに参加するならDAI、といったように、用途や目的に合わせた選択が重要です。特にアルゴリズム型はリスクが高いため、初心者は慎重に扱いましょう。
ステーブルコインの使い道とは?決済・投資・DeFiでの活用例


ステーブルコインは、価格が安定しているという特性から、暗号資産の中でも実用性が高く、さまざまなシーンで活用されています。ここでは、実際に使われている代表的なケースとして、「海外送金」「DeFi(分散型金融)」「投資のヘッジ手段」といった用途を紹介します。
海外送金・国際決済
● 銀行を介さない、速くて安い送金手段
ステーブルコインは、国際送金の分野で特に注目されています。
理由はシンプルで、従来の銀行送金と比べて:
- 送金スピードが早い(数分〜数時間)
- 手数料が格安(または無料)
- 仲介業者を介さずに個人間で送金できる
例えば、USDCを利用すれば、アメリカからフィリピンへ送金するのに銀行を使わずに直接、ほぼ即時で送金できます。受け取った側は、ステーブルコインを法定通貨に換金するだけ。特に、送金コストが高い国や、銀行インフラが未整備な地域での活用が進んでいます。
● 為替リスクの回避にも有効
また、ビットコインのような価格変動の大きい通貨では、送金中に価値が下がってしまうリスクがありますが、ステーブルコインならその心配もありません。
DeFi(分散型金融)での活用
● ステーブルコインはDeFiの基盤資産
ステーブルコインは、DeFi(分散型金融)サービスで最も利用されている資産の一つです。
- 貸し借り(レンディング):USDCやDAIを預けると利息が得られる
- 流動性提供(LP):DEX(分散型取引所)で通貨ペアの一部として提供
- ステーキング:スマートコントラクトに預けることで報酬を得る
● なぜDeFiではステーブルコインが人気?
価格が安定しているため、DeFiの複雑な取引でも価値の変動リスクを抑えやすく、安全に運用できるのが理由です。特にボラティリティの高い暗号資産に比べて、ステーブルコインは低リスクな利回り運用ができる手段として人気です。
暗号資産投資のヘッジ手段として
● 暗号資産のボラティリティ対策
ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、価格変動が非常に大きいため、利益を出す一方で大きな損失も起こり得ます。そんなとき、一時的にステーブルコインに換えておくことで、損失リスクを抑えることができます。
- 相場が不安定なときにBTCをUSDCに変えておく
- 利益確定後、価格下落に備えてDAIに逃がしておく
- トレードの合間にUSDTで資金を保管
このように、資産の一時退避場所(セーフゾーン)としての役割を果たすのがステーブルコインの強みです。
● リバランスやドルコスト平均法にも活用
定期的な資産リバランスを行う際や、長期投資でドルコスト平均法を実践する場合にも、ステーブルコインは分散投資の一部として便利です。
ステーブルコインは「使える暗号資産」
| 用途 | 特徴 |
|---|---|
| 海外送金 | 高速・低コスト・為替リスク回避 |
| DeFi運用 | 安定性が高く、リスク分散に最適 |
| 投資のヘッジ | 資産を守る「逃げ場」として有効 |
ステーブルコインは、単なる仮想通貨の一種ではなく、実用的な「使える資産」としての地位を確立しつつあります。
価格の安定性を武器に、個人投資家から企業、そしてDeFiユーザーにまで幅広く利用されており、これからのWeb3時代に欠かせない存在となるでしょう。
ステーブルコインの買い方と始め方|初心者におすすめの取引所も紹介


ステーブルコインは、暗号資産取引所を使って誰でも簡単に購入できます。しかし、「どこで買えるの?」「どうやって始めるの?」「安全な保管方法は?」といった疑問を持つ初心者も多いはず。
ここでは、ステーブルコインの購入方法から保管のポイントまでを、初心者向けにわかりやすく解説します。
購入できる主な取引所(国内/海外)
● 国内の暗号資産取引所
現在、日本の取引所では、法令上の規制によりUSDTやUSDCなどのステーブルコインは直接取り扱われていないことがほとんどです。そのため、日本円で直接ステーブルコインを購入することは難しく、多くのユーザーは以下の方法を取ります:
- 国内取引所でBTCやETHなどを購入
- 海外取引所に送金し、ステーブルコインに交換
- bitFlyer(ビットフライヤー)
- Coincheck(コインチェック)
- GMOコイン
- bitbank(ビットバンク)
● 海外の暗号資産取引所
海外の取引所では、USDT・USDC・DAIなどのステーブルコインを豊富に取り扱っています。
- Binance(バイナンス)
- Bybit(バイビット)
- OKX
- MEXC
これらの取引所では、BTCやETHといった暗号資産をステーブルコインに**簡単にスワップ(交換)**できます。
購入までの流れ(アカウント作成〜取引)
ステーブルコインを手に入れるためのステップは、大きく分けて以下の通りです。
Step 1:国内取引所で口座開設・日本円を入金
- 本人確認(KYC)を済ませ、取引アカウントを開設
- 銀行振込またはコンビニ決済で日本円を入金
- ビットコインやイーサリアムなどを購入
Step 2:海外取引所のアカウント作成
- 海外取引所(例:BinanceやBybit)でも口座を作成
- 二段階認証や本人確認を行い、セキュリティを強化
Step 3:暗号資産を海外取引所へ送金
- 国内取引所から、購入した暗号資産(BTC/ETHなど)を海外取引所のウォレットアドレスへ送金
- 送金時はアドレス間違いに注意!ブロックチェーンは一度送ると取り消しできません
Step 4:ステーブルコインへ交換(スワップ)
- 海外取引所でBTC/ETH → USDT/USDCなどに交換
- 現在のレートとスプレッドを確認し、最小限のコストで取引を行う
保管方法と注意点(ウォレットの種類など)


ステーブルコインを購入した後は、どこに保管するかが非常に重要です。特に大きな金額を保有する場合、取引所に置きっぱなしにせず、安全なウォレットを使いましょう。
● 保管方法の種類
| 保管方法 | 特徴 |
|---|---|
| 取引所内ウォレット | 初心者向け。手軽だがセキュリティ面ではやや不安 |
| ソフトウェアウォレット | スマホアプリやPC上で使える。代表例:MetaMask、Trust Wallet |
| ハードウェアウォレット | 物理デバイスでオフライン管理。最高レベルの安全性。代表例:Ledger、Trezor |
● 初心者には「ソフトウェアウォレット」がおすすめ
- MetaMask(メタマスク):使いやすく、DeFiにも対応
- Trust Wallet:スマホ対応で利便性が高い
● 保管時の注意点
- シードフレーズ(秘密鍵)は絶対に他人に教えない
- オンラインに保存せず、紙に書いて安全な場所に保管
- フィッシング詐欺や偽サイトに要注意!公式リンクを確認
ステーブルコイン購入は「国内+海外」取引所の併用がカギ
ステーブルコインを安全に購入・保管するには、次のポイントを押さえましょう:
- 国内取引所で日本円→BTCやETHを購入
- 海外取引所でステーブルコインに交換
- 信頼できるウォレットで安全に保管
一見複雑に見えるかもしれませんが、慣れればとてもシンプル。
資産の安定運用やDeFiの入り口として、ステーブルコインは非常に有用な存在です。
ステーブルコインのリスクと注意点|安全に使うためのポイント


ステーブルコインは価格が安定しているため「安全」なイメージを持たれがちですが、実際にはいくつかのリスクも存在します。特に、信頼性・規制・ハッキングといった側面には十分な注意が必要です。ここでは、ステーブルコインを安全に使いこなすために知っておくべきリスクと、その対策を解説します。
信頼性・裏付け資産の透明性
● 担保資産の不透明さに要注意
ステーブルコインの価値は「何を担保にしているか」に大きく左右されます。例えば、USDT(テザー)は米ドルに裏付けられているとされてきましたが、過去には準備資産の内容や比率について透明性が疑問視されたこともあります。
一方、**USDC(USDコイン)やDAI(ダイ)**は、定期的に担保状況の報告を行っており、比較的透明性が高いと評価されています。
● チェックすべきポイント
- 監査レポートを公開しているか
- 担保の内容(現金?債券?暗号資産?)は明確か
- 万が一、償還が必要になったときの対応力があるか
価格が1ドルで安定しているように見えても、裏付け資産が信頼できなければ「デペグ(価格乖離)」のリスクが発生します。
規制リスクと法的立場(国ごとの違い)
● 国や地域によって規制状況が異なる
ステーブルコインに関する規制は、各国で対応が分かれています。
以下は一例です:
| 国・地域 | 規制状況 |
|---|---|
| アメリカ | 発行者に対する監督強化中。ステーブルコイン法案の策定中 |
| 欧州(EU) | MiCA規制により規制の枠組みが整備されつつある |
| 日本 | 2023年6月より、**ステーブルコインを「電子決済手段」**として定義。発行者に免許が必要 |
| 中国 | 暗号資産全体を禁止しており、ステーブルコインも使用不可 |
● ユーザーへの影響は?
- 急な規制変更により取引停止や利用制限の可能性あり
- 一部の取引所でステーブルコインの取り扱いが制限されることも
- 税務処理や申告義務も国によって異なるため要確認
ステーブルコインは法定通貨に近い性質を持つため、将来的な規制強化の可能性が高く、利用前に自国の法律や最新の動向を把握することが重要です。
ハッキング・詐欺などのリスク管理
● ウォレット・取引所へのハッキング被害
ステーブルコインそのものではなく、それを保有するウォレットや取引所がハッキング被害に遭うケースは過去にも多く報告されています。
- 例:取引所の秘密鍵流出による盗難
- 例:フィッシング詐欺により、ウォレットの資金が抜き取られる
● 自衛手段としてのリスク管理
| 対策 | 説明 |
|---|---|
| 二段階認証の設定 | アカウントの乗っ取りを防ぐ基本 |
| ハードウェアウォレットの使用 | オフライン保管でセキュリティ性◎ |
| 公式サイト・アプリのみ使用 | 偽サイトや偽アプリに注意 |
| 秘密鍵やシードフレーズの厳重管理 | 紛失・漏洩は資産の喪失に直結 |
● DeFi関連のリスクにも注意
- スマートコントラクトのバグや脆弱性
- 詐欺的プロジェクト(rug pull など)への参加
- 高利回りをうたう怪しいサービスには要警戒
特に、DeFiでステーブルコインを運用する場合は、事前にプロジェクトの信頼性や監査状況を確認することが必須です。
価格が安定していても「ノーリスク」ではない
ステーブルコインは一見安全に見えますが、担保の信頼性・規制・セキュリティリスクなど、さまざまなリスクが存在します。
安全に使うためのポイント:
- 信頼できる発行元や取引所を選ぶこと
- ウォレットの管理を徹底すること
- 各国の法規制やリスクに常にアンテナを張ること
これらを意識することで、ステーブルコインのメリットを最大限に活かしつつ、リスクを最小限に抑えることができます。
まとめ


ステーブルコインは、価格が安定している暗号資産として、近年ますます注目を集めています。
- ステーブルコインとは米ドルなどの法定通貨に価値が連動した暗号資産でUSDT、USDC、DAIなどが代表例です。
- ステーブルコインはビットコインやイーサリアムとは異なり、価値保存・決済手段としての用途が中心で投資対象というよりも、安定した資産管理のツール
- リスクと注意点担保資産の透明性や、国ごとの規制動向に注意ウォレット管理やハッキング対策も必須
ステーブルコインは、「投機」ではなく実用的な資産管理・決済の手段として非常に有効です。特にこれからDeFiに触れてみたい方や、海外送金・安定運用を検討している方にとって、ステーブルコインの理解と活用は欠かせない知識となるでしょう。
安心して使える国内取引所で暗号資産を始めたい方は、下のボタンからbitFlyer(ビットフライヤー)公式サイトへアクセスして、無料口座開設をしてみましょう!


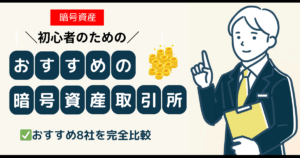



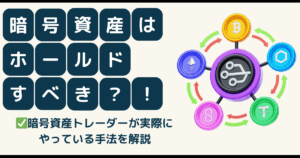


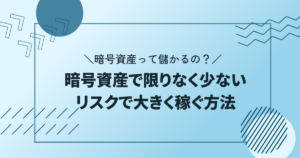
コメント